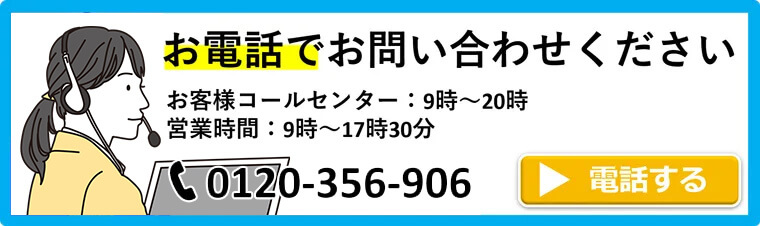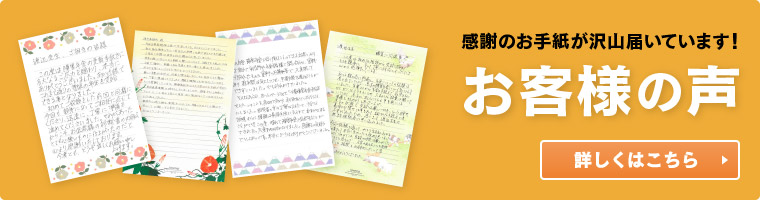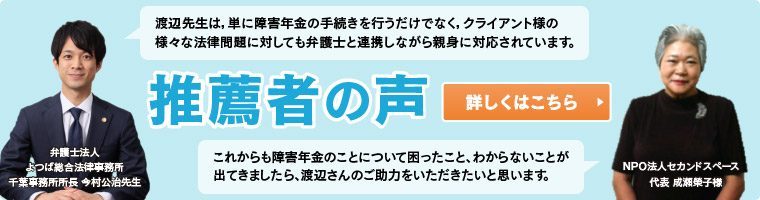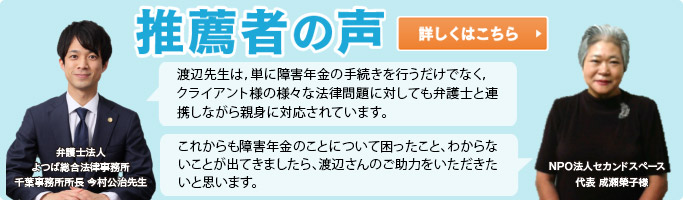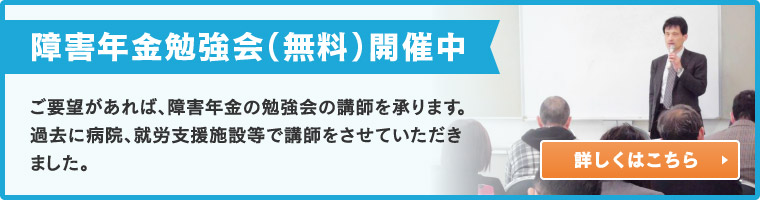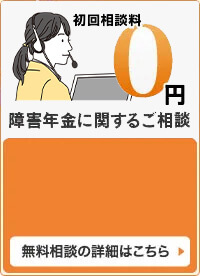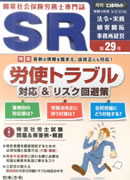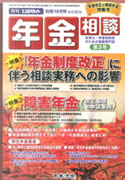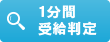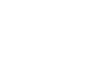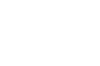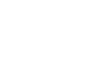人工血管・ステントグラフトで障害年金はもらえる?認定基準と申請のポイントを社労士が解説!
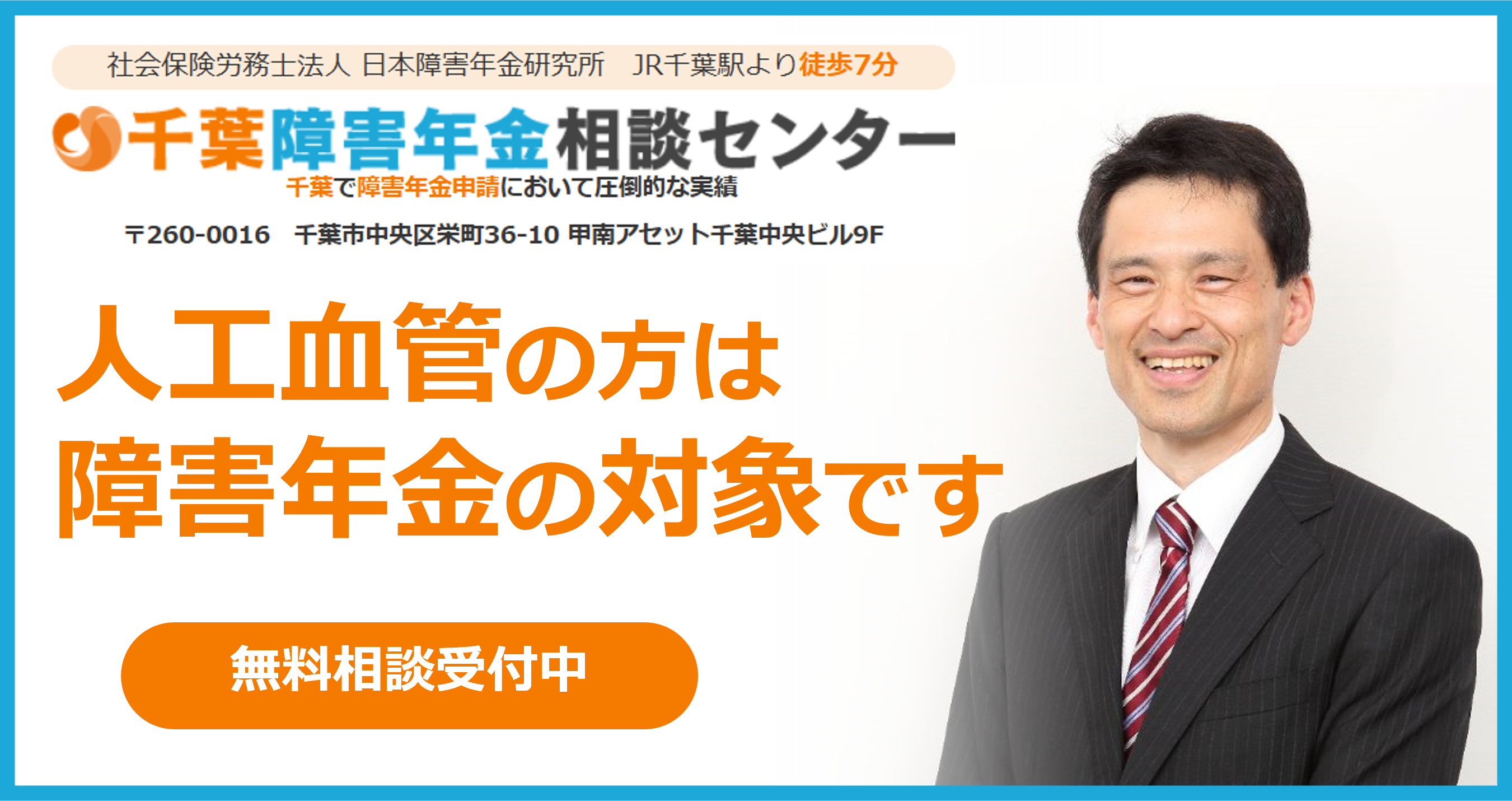
はじめに
大動脈瘤や大動脈解離などのご病気で、人工血管の置換術やステントグラフトの内挿術を受けられた方、またそのご家族の方へ。
手術が無事に終わり、ひと安心されたことと思います。しかし、同時に「術後の体調で仕事は続けられるだろうか?」「日常生活への影響は?」「経済的な不安がある…」といったお悩みを抱えていらっしゃる方も少なくないでしょう。
そのような状況で、生活を支える制度の一つが「障害年金」です。
「人工血管やステントグラフトを入れたら、障害年金はもらえるの?」
「どのような状態なら対象になる?」
「申請はどのように進めればいい?」
この記事では、このような疑問にお答えするため、人工血管・ステントグラフトと障害年金の関係、認定基準、申請のポイントについて、障害年金専門の社労士が分かりやすく解説します。
そもそも障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって、法律で定められた「障害の状態」になり、働くことや日常生活に支障が出ている場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる公的な年金です。
障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかによって、「障害基礎年金」「障害厚生年金」のいずれか、または両方が支給されます。
人工血管・ステントグラフトは障害年金の対象となるのか?
結論から申し上げますと、人工血管の置換術やステントグラフトの挿入術を受けた場合、障害年金の対象となる可能性があります。
障害年金の認定においては、「循環器系の障害」の一部として評価されます。
ただし、手術を受けたという事実だけで自動的に障害年金がもらえるわけではありません。障害年金を受け取るためには、以下の3つの基本的な要件を満たした上で、術後の状態が、国が定める障害認定基準に該当すると判断される必要があります。
障害年金を受給するための3つの基本要件
- 初診日要件: 障害の原因となった病気やケガで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が特定できること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの公的年金(国民年金、厚生年金保険)の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。(特例あり)
- 障害状態要件: 初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)、またはそれ以前でも症状が固定したと認められる場合に、その時点の障害の状態が、国が定める障害等級(1級・2級・3級)に該当すること。
人工血管・ステントグラフトにおける障害認定基準
人工血管・ステントグラフトに関する障害状態の認定は、「胸部大動脈(解離性を含む)に人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入(置換)し、かつ一般状態区分表のイエはウに該当するもの」が障害等級3級に認定すると定められています。
| 区分 | 一般状態 |
|---|---|
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
【ポイント】
- 厚生年金加入者が対象: 障害等級3級は、障害厚生年金の制度です。したがって、初診日に厚生年金に加入していた方が対象となります。(初診日に国民年金加入だった場合は、障害基礎年金となり、1級・2級のみのため原則対象外となりますが、他の障害との組み合わせ等で可能性がないわけではありません。)
- 術後の状態で判断: 最も重要なのは、手術を受けた後の身体の状態です。後遺症の有無や程度、日常生活や労働能力への影響が総合的に評価されます。
申請手続きの重要ポイント
人工血管・ステントグラフトで障害年金を申請する際に、特に注意すべき点を解説します。
- 初診日の証明:
- 障害年金申請の出発点であり、非常に重要です。
- 胸部大動脈瘤や大動脈解離は、健康診断で指摘されたり、別の病気の検査で偶然見つかったり、突然の発症で救急搬送されたりと、初診の状況が様々です。
- 最初に受診した医療機関で「受診状況等証明書」を取得する必要があります。カルテが破棄されている場合など、証明が難しいケースもありますので、早めの確認が重要です。
- 診断書(様式第120号の6 循環器疾患用):
-
- 障害の状態を証明する最も重要な書類です。
- 医師に依頼する際は、単に「人工血管を入れた」という事実だけでなく、「術後の具体的な症状」「検査数値」「日常生活や仕事への支障」「合併症の有無」などを正確かつ詳細に記載してもらうことが重要です。
- 特に、「一般状態区分表」のどの区分に該当するかは、等級判断に大きく影響します。ご自身の状態をしっかりと医師に伝えましょう。
- 病歴・就労状況等申立書:
- 発症から現在までの経過、日常生活や就労状況の変化などを、ご自身の言葉で具体的に記載する書類です。
- 診断書だけでは伝わりきらない、生活上の困難さや就労への支障を具体的に伝えることで、障害状態の判断を補強する重要な役割を果たします。
- 「いつから、どのような症状で困っているか」「仕事や家事で、具体的にどのような作業が難しいか」「周囲のサポートはどの程度必要か」などを、時系列に沿って詳しく記載しましょう。
申請の難しさと社労士に依頼するメリット
障害年金の申請は、必要書類が多く、制度自体も複雑です。特に人工血管・ステントグラフトの場合、
- 初診日の証明が難しいケースがある
- 診断書の記載内容が等級認定に直結するため、医師との連携が重要
- 病歴・就労状況等申立書で、日常生活や就労への影響を具体的に伝える必要がある
など、専門的な知識や経験が求められる場面が多くあります。
書類の不備や記載内容の不足で、本来受給できるはずの年金が不支給となったり、低い等級で認定されたりするケースも少なくありません。
私たち障害年金専門の社労士は、
- 複雑な制度や手続きを熟知しています。
- 初診日の証明や必要書類の収集をサポートします。
- 診断書作成について、医師に的確な情報提供や依頼を行います。
- ご本人の状況を丁寧にヒアリングし、実態に即した病歴・就労状況等申立書を作成します。
- 年金事務所とのやり取りや、万が一不支給となった場合の不服申し立て(審査請求・再審査請求)までサポートします。
ご自身での申請に不安がある方、手続きが難しいと感じる方は、ぜひ一度、障害年金専門の社労士にご相談ください。当センターでは初回相談は無料で行っております。
当事務所(千葉障害年金相談センター)に依頼するメリット
障害年金専門の社労士の中でも、当事務所にご依頼いただくことには、次のようなメリットがあります。
- 循環器疾患の申請実績が豊富: 当事務所は、千葉県を中心に数多くの障害年金申請をサポートしており、特に人工血管・ステントグラフトを含む循環器疾患の申請について豊富な経験とノウハウを有しています。実際の人工血管(ステントグラフト)の受給事例も多数ございますので、安心してご相談ください。
- 丁寧なヒアリングと書類作成サポート: お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、障害年金受給の可能性や見通しを的確に判断します。等級認定の鍵となる診断書については、医師に的確な情報提供を行い、実態に即した内容となるようサポートします。また、病歴・就労状況等申立書も、お客様の負担を軽減しつつ、日常生活や就労の支障が審査側にしっかりと伝わるよう、きめ細かく作成支援を行います。
- 手続きの負担を大幅に軽減: 複雑な書類の準備や年金事務所とのやり取りなど、申請にかかる時間と手間のかかる作業を代行します。お客様は治療や体調管理に専念いただけます。
- 初回無料相談の実施: 「自分の場合はどうだろうか?」「費用はどれくらいかかる?」といった疑問や不安にお答えするため、無料相談を実施しています。まずはお気軽にご連絡いただき、受給の可能性や当事務所のサポート内容についてご確認ください。
まとめ
人工血管置換術やステントグラフト内挿術を受けられた方は、その術後の状態によって障害年金3級に認定される可能性があります。
ただし、そのためには、初診日要件・保険料納付要件を満たし、ご自身の障害状態を診断書や申立書で的確に証明する必要があります。
手続きに不安がある、何から始めれば良いかわからない、という方は、決して諦めずに、私たち専門家にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適なサポートを提供し、障害年金の受給という経済的な安心を得るお手伝いをさせていただきます。